富士通はいかにジョブ型人事制度を企業変革のドライバーとして位置づけたか(1)―経営層・人事・社員が明かす現場変革の実態―
第1回(前編):経営層と現場社員が語る!ジョブ型人事制度導入の光と影
- 関連キーワード:

日本企業においても導入が進むジョブ型人事制度。富士通も全社変革プロジェクト「フジトラ(※1)」の一環として同制度を2020年度から幹部職員、全社員へと順次展開してきた。2026年4月入社からの新卒採用にも適用する予定だ。かつては成果主義を先行導入したものの、修正を迫られた経験を持つ富士通。今回のジョブ型人事への移行は、富士通の経営改革の一環で進めてきたが、どのようなビジョンを持って進めてきたのだろうか。その取り組みを前編・後編にわたって紹介する。
今後、日本企業は、組織運営のあり方のアップデートを迫られる。AIが浸透する社会においては、各組織のあるべき姿に基づき、我々”人間”が価値を生み出すべき仕事と、より効率化していく仕事を見極め、再定義することになる。新たな組織と“人”のあり方を定め、仕事を再定義するうえで適材・適所は避けられない。そして、適材・適所を実現するうえでは、リスキリングやアップスキリングも必要になるだろう。こうした課題への1つの有効なアプローチとして、ジョブ型人事が挙げられる。富士通は新たな組織のあり方とジョブ型人事の導入に基づき、意義ある仕事を生み出すべく企業変革を進めてきたのである。
本コラムの前編では、まず、「フジトラ」を牽引してきた富士通のエンタープライズ事業CEOである福田譲氏に人事改革の取り組みとその狙いについて伺い、さらに、Ridgelinez 上席執行役員Partnerの石田秀樹による富士通社員へのインタビューで人事制度改革の実態に迫る。後編では、富士通で人事企画部長としてジョブ型人事を推進し、現在RidgelinezでSenior Managerを務める黒川和真が現場で推進した取り組みを紹介する。
※本記事は、2025年8月29日に開催されたRidgelinez主催セミナー「変革実践者が本音で語る、富士通の【ジョブ型人事】の解体新書」の講演内容に基づき記事化したものです。所属・役職は掲載時点のものです。
利用者の8割がポジティブな評価をした「ポスティング制度」―ポスティング制度の効果と社員の反応―
「フジトラ」とは、2020年に始まった富士通の全社DXプロジェクトである。富士通はDXの推進にあたり「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」というパーパスを掲げ、「社会課題解決×テクノロジー×グローバル」を起点にビジネスを展開することを明言。その実現のために事業の変革(CX)、人・組織・カルチャーの変革(EX)、マネジメントの変革(MX)、オペレーションの変革(OX)という4つのXを推進している。
この4つのXのうち「人・組織・カルチャーの変革」の側面から進められてきたのが、ジョブ型人材マネジメントへのフルモデルチェンジである。
会社主導の異動や昇進ではなく、社員の自律的キャリア形成を促す「ポスティング制度(※2)」を導入。制度利用者は着実に増加し、2020から2023年の4年間で国内応募者は約2万7,000人、異動者は約1万人に達した。
さらに、ポスティング異動者への調査では、異動の前後で「自分の強みを活かせていると感じるか」、「自分の成長を感じるか」という2つの質問をしたところ、異動後においては8~9割の社員がポジティブな回答を寄せている。「自分でキャリアを選択したことが、仕事のやりがいにつながっている」と福田氏は自信を覗かせた。
2026年4月入社からの新卒についても総合職一括採用ではなくジョブ型採用へ切り替えるという富士通。グループ共通のグローバル人事システム「One People」を構築し、全世界共通の基盤に基づいたデータドリブンHRも推進中だ。
(※1)フジトラ:「顧客や社会のDXをサポートするためには、まず富士通自身のDXが必要」との認識に基づき、開始された全社DXプロジェクト。「経営のリーダーシップ」、「現場の叡智を結集」、「カルチャー変革」の3点を重点テーマに掲げ取り組みを進めている。
(※2)ポスティング制度:社員自ら手を挙げて、部署を異動できる制度。富士通グループ内の空きポジションが常時公開されており、自身の志向・キャリア開発に応じて自ら応募・挑戦できる。上位職のポジションへの挑戦(昇格)や海外ポジション(グローバルポスティング)もあり、多くの社員が活用している。
ジョブ型人事制度を活用した現場社員の視点
では、「フジトラ」や前述した富士通の経営改革の一環である人事改革の取り組みを、当事者である富士通社員はどのように受け止めているのか。 コーポレートデジタル本部 Senior Manager 竹内裕子氏、AI戦略・ビジネス開発本部 Senior Manager 寺島眞生氏、CEO室 Data & Process Division Manager 碁盤亜伊子氏の3名は、いずれもポスティング制度を利用し、同時に管理職への昇進を果たした。それぞれが制度を活用して得られたメリットや本音を語る。
1.「フジトラ」は現場にどのように受け止められてきたのか
石田 皆さんはポスティング制度をうまく活用し、昇進も果たされた立場です。福田さんは「フジトラ」を仕掛けた側ですが、仕掛けられた側の皆さんは、この変革をどのように受け止めましたか。
寺島 私が今、富士通で働けているのは、「フジトラ」や人事改革のおかげだと思います。ポスティング制度を3回活用していますが、その都度、新たな仕事を通して得意領域を発見し続けてきました。その過程で、ジョブグレードが上がるにつれて裁量も大きくなっていき、入社5年目でSenior Managerに昇格しました。
石田 寺島さんのキャリアは順風満帆に見えます。富士通の「フジトラ」や人事改革におけるポスティング制度という土壌が無かった場合、現在も、富士通に在籍し、働き続けていたでしょうか。
寺島 いえ。可能性として退職の選択肢もあったかもしれません。
石田 一方で、ポスティング制度の改定後には、それが受け入れられず、退職を選ぶ方もいますよね。
寺島 私は「ワクワクする世界を作る、生きる、分かち合う」というパーパスにたどり着きましたが、退職を選んだ社員は自分のやりたいことやパーパスを言語化できず転職を選んだのではないかと思います。
石田 自身の想いを言語化ができると、キャリアの中で仕事の位置付けを探究するということにつながると思います。碁盤さんは「フジトラ」や人事改革をどのように受け取りましたか。
碁盤 私はシリコンバレーに駐在していました。海外ではジョブごとに雇用される文化があるため、特定の仕事に対して自ら応募するというポスティング制度を違和感なく受け止めることができました。当初は懐疑的な社員も多かったと思いますが、ITの仕組みの変更や人材の入れ替わりを経験する中で、「変わるしかない」という認識に変わっていったように思います。
石田 実際にポスティング制度を活用して異動した社員を周囲はどのように見ていましたか。
碁盤 「前の職場が合わなかったのか」とネガティブな捉え方もあれば「新たな挑戦をしたいなら当然」と肯定的な見方もありました。引き止めることもありますが、最終的には「新天地でも頑張って」と送り出すことが多いですね。

2.ポスティング制度を通して問い直されるキャリア観
石田 皆さんにとって、ポスティング制度は働き方を大きく変える契機となりましたが、意図的に居場所を変えた動機は何でしょうか。
竹内 自分にも選択肢があると気づいたことです。私は「自由に楽しく世界とつながる」というパーパスを掲げ、「自由」を大切にしてきました。しかし、先日、後輩に「いつ出張に行きますか?」と聞かれた時、これまで自分は子供がいるので出張はできないと思い込んでいたことに気づかされました。自ら「自由」を制限し、選択肢を狭めていたのです。それ以降は「英語を使いたい」「海外出張したい」といった想いを表出することができるようになりました。
石田 無意識に諦めていたことに気づけたのが転機だったということですね。
寺島 私は、自分の弱みを補完するために意図的に居場所を変えました。若いうちに責任あるポジションを任され、顧客から「その若さで課題を解決できるのか」と常に問われましたので、必要な経験と知識を最短で積むために、プロジェクトを戦略的に渡り歩き、強制的に学習機会を増やそうとしたのです。
石田 自らを挑戦に追い込むストイックな姿勢によって、見える景色は大きく変わりますよね。
碁盤 私は、子どもの成長に合わせてキャリアを考えた結果、自然に仕事を変えることになりました。子どもが1歳になるまでは在宅中心、その後は出社を増やすといった具合です。ただ、一歩を踏み出せない社員が多いのも事実。メンタリングしていた女性社員は、ポスティング制度でマネージャーに昇格するか迷っていました。意欲がある方やパフォーマンスが素晴らしい方でも最後の1歩が踏み出せないという時は、周囲が後押しすることも必要だと感じました。
石田 会社としては制度だけでなく背中を押すような仕掛けが必要かもしれませんね。
3.制度を通して見えてきた課題
石田 これまで現場の皆さんの感想を伺いましたが、「仕掛けた側」として福田さんから社員に尋ねたいことはありますか。
福田 新しい人事評価制度が浸透する中、課題だと感じていることを教えてください。
碁盤 まずは人材流出対策です。大部分の人材が抜けた部署もあると聞いています。また、ポスティングで入った人材が短期間で辞めるケースもあるので、一定期間の在籍を条件とする仕組みがあってもよいと思います。
寺島 確かに、人が集まらない部署があると感じます。「フジトラ」への温度感も部署ごとに違い、理念に基づいた提案が保守的な部署に却下されることがあるのも悩みの種です。
竹内 私は「やりたいことをやっていい」というメッセージを周囲に広めたいとずっと思い続けてきましたが、そのように広くメッセージできるようになったのはSenior Managerという肩書きのおかげでした。でも、本来は肩書きがなくとも「チャレンジしたいことをやっていい」と広くメッセージできるのが理想なので、そのようなチャレンジしていく行動が社員の目に留まるような仕掛けがあればよいと感じます。
石田 率直な意見を言えるという風土を醸成することは、一朝一夕には難しいことだと感じます。示唆に富むお話をいただき、ありがとうございました。
本コラムから得られた示唆―次回のコラムに向けて―
今回のコラムでは、富士通CEO福田譲氏が語る富士通の変革実践と、ポスティング制度を自らの発意をもって実践してきた現場社員の方々の原体験を共有いただきました。変革実践の裏話と現場社員のリアルな本音からポスティング制度を肯定的に捉えるケースが浮かび上がりました。他方で、自律的なキャリア観の広がりと同時に、ポスティング制度による人材流出、フジトラ施策に対する“温度差”、ジョブディスクリプション(以下、JD)(※3)の必要性に対する各部署の理解度といった課題も無視できません。
後編では、こうした論点に正面から向き合い、JD作成の難しさ、人材流出への対応策、運用のプロセス、そしてジョブ型の可能性に対して、人事企画の当事者である黒川が具体的な事例を通して語ります。富士通がどのように「制度を文化へ」と根付かせようと実践してきたのか、そのプロセスと学びをRidgelinezの視点から探ります。
(※3)ジョブディスクリプション(JD):職務内容や責任範囲、必要なスキルなどを具体的に記述した文書。
登壇者プロフィール
福田譲 氏
富士通株式会社 エンタープライズ CEO
1997年 SAPジャパンに入社。ERP導入による業務改革、経営改革、高度情報化の活動に従事。2014年、SAPジャパン代表取締役社長に就任。2020年、富士通に入社。執行役員常務 CIO 兼 CDXO補佐として、富士通の変革を実現する全社DXプロジェクト「フジトラ(Fujitsu Transformation)」などを主導する。2023年にCDXO兼CIO。2025年4月から執行役員専務 エンタープライズ事業CEOに就任。
石田 秀樹
Ridgelinez株式会社 上席執行役員Partner People Transformation Practice Leader
金融・製造・通信・ハイテクの各業界を中心とした20年以上のコンサルティング経験に基づいた「人起点」の実践的な変革支援を得意とする。事業戦略策定、人財戦略策定(人的資本経営の実践)、組織構造変革(DX推進組織設計・グループガバナンス)、人事機能変革、Employee Experience視点でのワークスタイル変革、人事基幹システム構築、組織風土変革、リスキリング実行支援、People Analytics(人財情報分析による変革アプローチ)等の支援を数多く手掛けた経験を有する。
黒川 和真
Ridgelinez株式会社 Senior Manager
富士通HRの人事制度企画などCoEに16年間従事。ジョブ型人材マネジメントへのフルモデルチェンジ関連では、Global Role Framework、JD、組織ポジション設計、評価・報酬制度、採用強化、ポスティング制度などを人事企画部長として担当。その他に役員人事、指名委員会・報酬委員会などのコーポレートガバナンス、労政、経団連等の社外団体対応などのCoE業務を担当。2025年よりRidgelinezに出向し、シニアマネージャーと富士通CHRO室シニアディレクターを兼務。






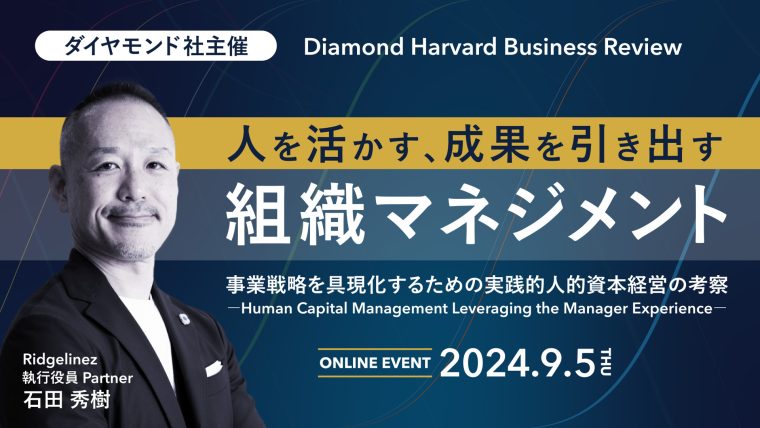


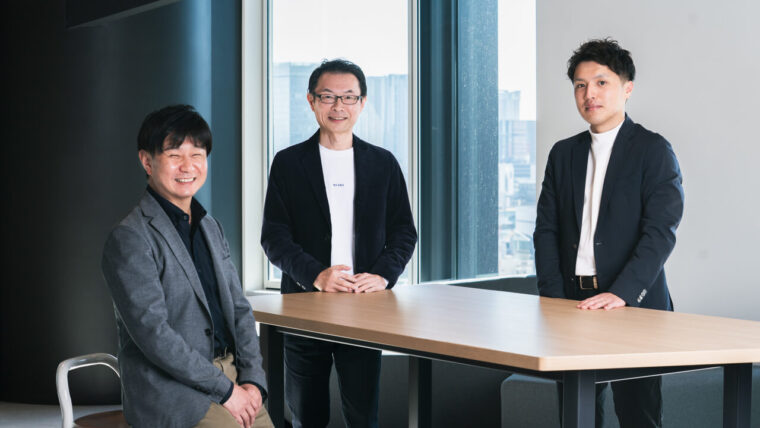
 共鳴する社会展
共鳴する社会展