富士通はいかにジョブ型人事制度を推進したか(2)―経営層・人事・社員が明かす現場変革の実態―第2回(後編):人事企画の担当者が語る、ジョブ型人事制度の舞台裏
- 関連キーワード:

日本企業においても導入が進むジョブ型人事制度。しかし、その導入には多くの障壁がつきまとう。本稿では、かつて成果主義の導入で苦渋を経験した富士通が、全社変革プロジェクト「フジトラ(※1)」と併せて、富士通の経営改革の一環として、いかにジョブ型人事制度を推進し、その障壁を乗り越えてきたのかに迫る。
前編では、「フジトラ」を牽引してきた富士通 エンタープライズ事業 CEO 福田譲氏と現場社員の話を通じて、ジョブ型人事制度がもたらした自律的なキャリア形成の「光」と、人材流出や現場の「温度差」といった「影」を紐解いた。
後編では、引き続きRidgelinez 上席執行役員Partnerの石田秀樹が、あらゆる課題に人事企画の当事者がどう向き合い、乗り越えようとしたのかを深掘りする。富士通 人事企画部長としてジョブ型人事を推進し、現在はRidgelinezでSenior Managerを務める黒川和真に、4万に及ぶJD設計の苦悩、人材流出への対応策、そして運用プロセスの現在地を伺った。
※本記事は、2025年8月29日に開催されたRidgelinez主催セミナー「変革実践者が本音で語る、富士通の【ジョブ型人事】の解体新書」の講演内容に基づき記事化したものです。所属・役職は掲載時点のものです。

約4万に上るジョブに対する試行錯誤―JD設計の困難と富士通の独自アプローチ―
石田 成果主義導入で苦戦した経験がある富士通にとって、ジョブ型は大きな挑戦だったと思います。特にジョブディスクリプション(以下、JD)(※2)の設計は困難だったのではありませんか。
黒川 本当に大変で、約4万のジョブをどう定義するか途方に暮れましたね。まずは人事がロールやタスク、スキルを整理してロールプロファイルを作成し、事業部のマネージャーには責任範囲のみ記載してもらうよう依頼しました。結果的に約8割の部署は記載してくれたのですが、残る約2割は極端な短文や空白のままでした。
石田 8割は当初の予想を超えた提出率だったのではないでしょうか。
黒川 予想よりは高かったと考えています。ひとまず全部署のJDを回収してAIで分析し、「どのような課題を解決するのか」というビジョンが書かれているJDが良さそうだと見当をつけました。そして自社開発した「JDメーカー」(※3)を参照しながら作成してもらうように促したところ、極端に短いJDは徐々に減っていきました。また、ポスティングでの人材募集やポストオフなどにJDが活用されることで、質が向上する事例もありました。
(※1)フジトラ:「顧客や社会のDXをサポートするためには、まず富士通自身のDXが必要」との認識に基づき、開始された全社DXプロジェクト。「経営のリーダーシップ」「現場の叡智を結集」「カルチャー変革」の3点を重点テーマに掲げ、取り組みを進めている。
(※2)ジョブディスクリプション(JD):職務内容や責任範囲、必要なスキルなどを具体的に記述した文書。
(※3)JDメーカー:作成難易度の緩和および、JDの役割・権限・責任範囲の明確化に向けた富士通オリジナルのJD作成支援ツール。
ポスティング制度による人材偏在への対応策
石田 従来の人事制度では“玉突き人事”での調整がありましたが、こうした複雑な調整を必要とする中でポスティング制度はうまく機能したのでしょうか。
黒川 もちろん、玉突き人事は現在も引き続き発生しています。ポスティングを原則として、ポジションが空けば、まず公募で全員に機会を与えるようにしていますが、重要ポジションに対しては特定のタレント人材を指名して配置することもあります。その場合は「その人材が元いたポジションにポスティングをかける」などの対応を行っています。
石田 社外から人材を募集することもあるのですか。
黒川 ポスティングをかける際は、社内公募と社外求人を同時に行っており、社外からの応募者を採用することも珍しくありません。
石田 ポストの人気差はどうしても出てきてしまうと考えますが、それをどのように調整してきましたか。
黒川 確かに不人気なポストはあり、人材流出する部署もあります。ただ、私は「良い職場にして、人材を奪い返すしかない」と伝えています。ジョブ型では、社内競争が前提になるので、仕事の面白さや醍醐味、獲得できるスキルや経験など、その部署で働く魅力を発信しなければ人は集まりません。
石田 異動する社員にとっては、仕事の内容だけでなく、職場の雰囲気も重要です。そのために、エンゲージメントサーベイの結果を組織単位で開示しているそうですね。
黒川 マネジメント変革につなげるには、そこまでやるべきだと考えています。各組織のトップには、人材獲得競争の責任を自覚してもらう必要があります。失敗すればポストオフ(※4)もあり得るという危機感こそが、組織力強化の原動力になるはずです。
石田 つまり、その責任を自覚していなければ、組織のトップは務まらないということですね。
(※4)ポストオフ:マネージャー、部長など、管理職ポジションに就いている者が役職から外れる制度。
運用プロセスの現在地
石田 立ち上げ期のJD作成では、ロールの定義は人事、責任範囲の定義は事業部が担っていたとのことですが、その後、ジョブ設計の権限は事業部側へ完全に委譲されたのですか。
黒川 そのとおりです。ただ、責任は完全に委譲しましたが、一部、事業部側が実施できないところもあると感じています。ジョブ設計は、事業戦略や外部環境の変化に応じて見直していく必要がありますが、それができておらず、“As-Is”(※5)にとどまる部署もあるためです。
石田 権限は委譲できているが、事業部長が組織の変更(廃止/新設も含む)などを自らが裁量を持って行うことができていないということですね。組織を変えていくことが自身の裁量であると自覚的に行動できている方とできていない方で差が出ているのでしょうか。
黒川 組織の戦略がAs-Isに寄りすぎてしまうという差があると思います。As-Isを知っているがゆえに、ポジションを減らすことへの抵抗が出たり、組織を変えていくこと自体が複雑で難しいと考えてしまったりするのかもしれません。
石田 それぞれの事業戦略を具現化していくうえでもポストオフの存在は非常に大きいですね。実際、どこまで適切に運用されているのでしょうか。
黒川 徐々に実践されていると考えます。ポストオフを制度として導入したとき、当時、年齢で一律実施する役職離任制度がありましたが、廃止しています。年齢ではなくポジションに求められる役割を果たせているかどうか等の異なる理由でポジションを外すポストオフ制度を運営していくかという時に、当初は「ポストオフを行う割合や人数の目安」を示していました。ただし、制度を変えても当初は年齢を理由にポストオフする職場が多く、若手マネージャー層からも「何も変わっていない」という声が寄せられたように、最初から年齢一律のマネジメントを簡単に脱却できたわけではありませんでした。
石田 昨年ポストオフ制度を見直したと聞きました。完全にジョブ型へ移行するために最後まで難航したのがポストオフ制度だったのでしょうか。
黒川 2020年に年齢一律の役職離任制度を廃止し、ポストオフ制度を導入はしましたが、最後まで運用を定着させるのが大変だったと思います。ようやく制度も定着してきたため、ポストオフ数の目安を一定比率で定めることを昨年からやめました。ポストオフ数の目安は提示していませんが、幹部社員のポジション数には限りがあるため、組織の状況に合わせてポストオフを実施し、空いたポジションに優秀な若手などを登用することは引き続き重視しています。
(※5)As-is:目指す方向性は、事業戦略を実現するために必要な組織やポジションの設計であったものの、現在行っている職務内容をJDとして言語化するだけにとどまってしまっているケースが多かった。
ジョブ型人事制度の可能性―より良い制度に進化していくために―
続いて黒川は、ジョブ型に関する富士通社員の質問に答えた。
竹内 私は以前在籍していた部署において、JDを見たことがありませんでした。異動先の部署でも、既存メンバーはJDの存在を知らないようだったので、まだそれほど浸透していないのではないでしょうか。
黒川 JDはあくまで作成が完了した段階であり、それを活用したマネジメントができているかどうかは別問題で、まだまだ深める余地があると考えています。
碁盤 私は異動先の上司に声をかけられて異動してきましたが、人を集める事に苦戦している部署だったのではないかと感じています。JDの質と人材の応募数の相関関係を示すデータなどはありますか。
黒川 精緻なデータ分析はしていませんが、JDの記述が不十分だと人材が集まらないという感覚はあります。JDの精度を上げることが、富士通全体で良い人材を獲得することにつながると考えています。
寺島 ジョブが部署によって異なる中、どのようにジョブグレードを標準化しているのですか。また、事業部側にジョブ設計の権限を委譲すると、評価の標準化が難しくなるのではないでしょうか。
黒川 ロールやレベルは、社内ではなく市場の標準をベンチマークにしています。例えば、売上規模や統括する組織規模などですね。評価の標準化については、確かに事業部ごとに「甘辛」が生じることはあります。しかし、「人の評価軸」は標準化しており、ロールの定義やレベルの基準といった評価そのものはグローバルで統一しています。
もちろん、その評価軸を用いた実際の判定は各事業部に委ねる形になり、「あの部署は評価が甘い」と指摘されることもありますが、こうした議論があることは健全であり、それによって徐々に標準化が進んでいくとも考えています。
本コラムから得られた示唆
今回は、富士通の「フジトラ」の推進を支援したRidgelinezの視点から、変革のポイントや社員が自らの発意をもって行動されてきた原体験の変化を捉えてきました。
ジョブ型人事およびJDの導入は、自らのキャリアをどのように歩んでいくか、社員それぞれがキャリアの岐路と向き合う仕掛けとなることが対談を通して明らかになりました。激しい変化の時代において、会社主導で仕事を再定義することは企業が目指すゴールに向け、個人のパフォーマンスを最大化したり、やりがいを向上したりすることにつながると強く考えさせられます。
まさに今回語られたポスティング制度は、個々の部門・部署が自分たちは何をするのか、何をするべきなのかと向き合わざるを得ない仕掛けとなりました。社員に対して、部門・部署が持つ仕事の意義、社会的な業務の重要性を説明することが求められています。Ridgelinezでは引き続き、企業変革に向けた人事が向かうべき未来の示唆 および ナレッジ蓄積に取り組み、企業の人的資本経営の推進を発信してまいります。
登壇者プロフィール
福田譲 氏
富士通株式会社 エンタープライズ CEO
1997年 SAPジャパンに入社。ERP導入による業務改革、経営改革、高度情報化の活動に従事。2014年、SAPジャパン代表取締役社長に就任。2020年、富士通に入社。執行役員常務 CIO 兼 CDXO補佐として、富士通の変革を実現する全社DXプロジェクト「フジトラ(Fujitsu Transformation)」などを主導する。2023年にCDXO兼CIO。2025年4月から執行役員専務 エンタープライズ事業CEOに就任。
石田 秀樹
Ridgelinez株式会社 上席執行役員Partner People Transformation Practice Leader
金融・製造・通信・ハイテクの各業界を中心とした20年以上のコンサルティング経験に基づいた「人起点」の実践的な変革支援を得意とする。事業戦略策定、人財戦略策定(人的資本経営の実践)、組織構造変革(DX推進組織設計・グループガバナンス)、人事機能変革、Employee Experience視点でのワークスタイル変革、人事基幹システム構築、組織風土変革、リスキリング実行支援、People Analytics(人財情報分析による変革アプローチ)等の支援を数多く手掛けた経験を有する。
黒川 和真
Ridgelinez株式会社 Senior Manager
富士通HRの人事制度企画などCoEに16年間従事。ジョブ型人材マネジメントへのフルモデルチェンジ関連では、Global Role Framework、JD、組織ポジション設計、評価・報酬制度、採用強化、ポスティング制度などを人事企画部長として担当。その他に役員人事、指名委員会・報酬委員会などのコーポレートガバナンス、労政、経団連等の社外団体対応などのCoE業務を担当。2025年よりRidgelinezに出向し、シニアマネージャーと富士通CHRO室シニアディレクターを兼務。






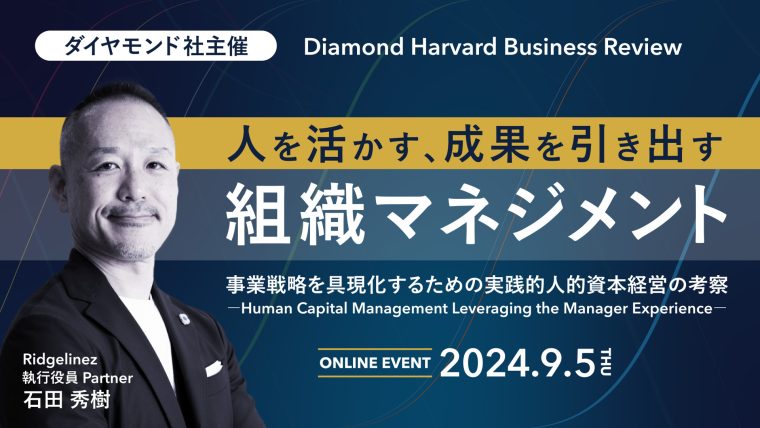


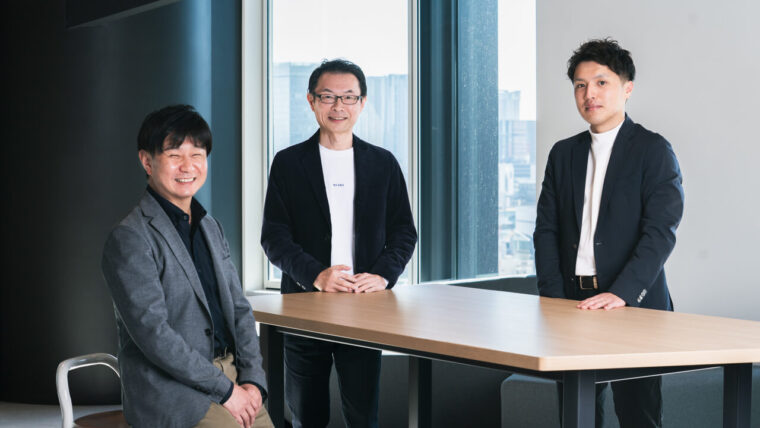
 共鳴する社会展
共鳴する社会展