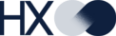テスラとアマゾンが実践、最先端の製造業DX 日本企業の挑戦
2022年12月20日

「ビッグデータ×AI(人工知能)」、クラウドコンピューティング、IoTといったテクノロジーを利活用し、設計・製造・保守などの現場業務をデジタル化することによって、新しい価値を創り出す。こうした製造業のデジタル・トランスフォーメーション(「製造業DX」)を加速する機運が、第4次産業革命を背景に高まっている。
そのような中、製造業DXに進出したメガテック企業がテスラとアマゾンだ。
EVメーカー テスラのイーロン・マスクCEOは工場を顧客向けプロダクトと捉え、「マシンである自動車を進化させるより、マシンをつくる工場を進化させた方が10倍も効果が高い」と言う。工場は、まさに「製造業DX」の実践の場なのだ。テスラの四半期ごとの株主向け開示資料には、すべての工場の製造能力や建設予定といった更新情報が必ず盛り込まれ、工場の生産性が戦略的に重視されていることが読み取れる。
EC・小売りからクラウド、金融、広告などを事業領域とするエブリシングカンパニー アマゾンも「製造業DX」に参入した。アマゾンは、機械学習を通して顧客工場の機器を予知保全する「Amazon Monitron(アマゾン・モニトロン)」、デジタルツインの構築と維持運用を簡単にする「AWS IoT TwinMaker (AWS IoTツインメーカー)」を立て続けに市場に投入。そこでの原動力は、創業以来変わることのないビジョンである顧客中心主義だ。
一方、日本を代表する伝統的メーカー 日立、パナソニック、東芝も製造業DXの動きを加速させている。製造業DXをめぐる戦いに臨む日本企業にとっての要諦は、いかに優れたカスタマーエクスペリエンス(顧客体験)を提供できるかにある。その意味で、日本企業が「BtoB事業者としての誇りを捨てる」ことができるかが重要だ。米国などのメガテック企業に挑戦するにあたり、日本企業には小手先でない本質的な革新が求められる。
目次
物理学的思考を工場に持ち込んだテスラ
米国で最も生産性の高い自動車工場、それはテスラのフレモント工場だ。
ブルームバーグは「2021年テスラのフレモント工場は70の北米自動車工場のどこよりも生産性に優れていた」と報じた(2022年1月24日付記事)。その製造能力は週平均8,550台。二番手につけたトヨタのジョージタウン工場は週平均8,427台だった。単位面積当たりの製造能力で見れば差は歴然とする。トヨタの9台(週平均、1万平方フィート当たり)に対しテスラは16台(同)。テスラの製造能力はトヨタの約1.8倍という計算になる。
テスラは、今年3月にギガファクトリー・ベルリン、4月にはフレモント工場の1.5倍の敷地面積を持つギガファクトリー・テキサスという2つの工場を新しく稼働させた。トヨタを超えるほどの生産性と量産体制を備えたテスラ。その強さの源泉はどこにあるのか。
テスラといえばEV車のメーカーとして知られるが、その本質は自動車企業ではなく、テクノロジー企業だ。テスラ車は常時インターネットに接続されており、ハード(車体)を刷新しないまま、自動運転などのソフト面の性能を高め続けている。スマホなどテクノロジー産業ではおなじみの「ソフトウェアをアップデートする」発想だ。
テスラの工場「ギガファクトリー」も革新的だ。大学で物理学を専攻したイーロン・マスクCEOは「現状や常識を疑う」という物理学的思考を工場に持ち込んだ。「工場もプロダクトであると考える」「工場を、マシンをつくるマシンと考える」「マシンである自動車を進化させるより、マシンをつくる工場を進化させた方が10倍も効果が高い」。いずれも16年株主総会での発言である。
また従来、工場といえば労働投入量や稼働率、労働分配率、在庫回転日数などを指標に運営されていた。だが、ギガファクトリーが重視するのは「アウトプット(生産台数)=ボリューム(生産規模)×密度(サプライヤーを含めた生産拠点の稠密性)×速度」の公式だという。なお密度とは、太陽光発電や蓄電池などの生産拠点をギガファクトリーに隣接させていることを指す。独自の組立ラインも速度に貢献している。車両がコンベアで運ばれてくるのが一般企業の工場とするなら、車両が無人搬送車の上に載せられてラインを流れてくるのがテスラの工場だ。これなら車両に不具合を見つけてもコンベアを止める必要がなく、不具合のあった車両だけを除けばよい。なにより、工場の拡張性、柔軟性、機動性の向上にも優れた手法といえるだろう。この手法は、生産プロセスの徹底的なデジタル化・同期化があって初めてなし得ることでもある。
ギガファクトリーとは、世界最先端の「製造業DX」実践の場だ。
アマゾンAWSはデジタルツインに進出
世界最強のテクノロジーカンパニーの1つであるアマゾンも製造業DXへと乗り出している。
アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)は、2020年12月に開かれた年次イベント「AWS リインベント2020」で「アマゾン・モニトロン」を発表した。AWSはアマゾンが提供するクラウドサービス。ストレージ、データベース、コンピューティングをはじめ、今やAIアプリケーションなど多様なサービスを提供する。「アマゾン・モニトロン」は工場にあるモーターやコンプレッサーなどの産業機器にIoTセンサーを取り付け、クラウド上にデータを吸い上げることで、機械学習を通して機器をモニタリング、「予知保全」プログラムを実行するというもの。故障や異常が発生してから対応を行う「事後保全」とは異なり、障害発生前にメンテナンスを行うことで、予定外のダウンタイムを削減できる。
翌年の「AWS リインベント2021」では新たに、デジタルツインの構築と維持運用を簡単にする「AWS IoTツインメーカー」を発表した。
従来、新しい製品をテストするには実際にモノを作る以外に方法はなかった。デジタルツインは、現実世界から収集したデータを「双子」のようにサイバー空間で再現する技術だが、データの収集など作業は煩雑である。しかし「AWS IoTツインメーカー」があれば、工場や建物などのデジタルツインを簡単に作成できる。例えば工場のデジタルツインを作成し、そのオペレーションをリアルタイムで監視する、生産性向上に向けてシミュレーションするなどの用途が期待される。室温や湿度、照度など環境に関する情報も吸い上げることができ、デジタルツインを利用して現場の安全衛生環境を改善するということも可能だ。
「AWSリインベント2021」を貫くテーマは「AWS がどのように企業のDXを簡単にするか」だった。しかしアマゾンは「BtoBとBtoCの利害が対立したらBtoCを選ぶ」と明言するほど、徹底した顧客中心主義(カスタマーセントリック)の企業であることを忘れてはならない。「AWS IoTツインメーカー」の根源にもカスタマーセントリックの発想がある。AWSの自社ブログでは、アマゾン・ジャパンのエンジニアが「AWS IoTツインメーカー」を活用して自分の部屋のデジタルツインを作成、それら「双子」をリアルタイムに同期させようと試みていた。開発者レベルのスキルが要求されるとはいえ、エンドユーザー自らデジタルツインを作成できる環境が「AWS IoTツインメーカー」によって実現しているのだ。
アマゾンの顧客中心主義は創業以来のビジョンであり、アマゾンを世界最強のテクノロジーへと押し上げた原動力そのものだ。それが製造業DXのサービスにも受け継がれているのだとすれば、製造業DXの覇権をもアマゾンは握りかねないのだ。
BtoB企業としての誇りを日本企業は捨てられるか
もちろん、日本の製造業もDXの動きを加速させている。
日立は、米国デジタルエンジニアリングサービス大手のグローバルロジックの買収を完了した(2021年7月)。同社はチップからクラウドに至るまで幅広い製品やサービスに対応するソフトウェア・エンジニアリング・サービスを提供。世界14か国に顧客との「協創」を加速するためのデザインスタジオなどの拠点を持ち、製造、通信、金融、自動車、小売り、ヘルスケアなどの業界向けにソフトウェア開発を行っている。
日立は同買収によってDXを加速し、「Lumada(ルマーダ)」関連事業をグローバルに拡大させる計画だ。ルマーダには、「顧客が持つデータに光をあて輝かせることで、新たな知見や価値を引き出し、顧客の経営課題の解決や事業の成長に貢献する」という日立の思いが込められている。ルマーダとはいわば、「IT×OT(オペレーション・テクノロジー)×プロダクト」により新しい価値を生み出すプラットフォームだ。今後日立は、ルマーダを基軸に顧客・パートナーとの共創を進め、IT、エネルギー、インダストリー、モビリティ、ライフの5セクターでの価値創出を図るとする。
パナソニックは米国サプライチェーン・ソフトウェア大手のブルーヨンダーを買収(2021年9月)。今年5月にはブルーヨンダーを中心とする事業について新会社を設立し、上場を目指す方針を明らかにした。ブルーヨンダーは、サプライチェーン分野でAIを活用した製品の需要や納期を予測するソフトウェア開発を手掛け、小売り、消費財、自動車、製造、ハイテク・半導体などの業界に約3,300社を顧客に持つ。パナソニックはブルーヨンダーを傘下に置くことで、パナソニックがメーカーとして持つセンシングやロボティクス分野のハードウェアに関する知見や経験と、ブルーヨンダーのソフトウェア、AIやコンピューティングに関する強みをかけ合わせ、サプライチェーン関連事業を強化・加速させる狙いだ。
東芝は「デジタル化を通じて、カーボンニュートラル・サーキュラーエコノミーの実現に貢献」すると謳う。今年3月に代表執行役社長CEOに就いた島田太郎氏は、直後に開催されたオンラインイベント「TOSHIBA OPEN SESSIONS」において「持続可能な社会の実現のためにはカーボンニュートラルとインフラレジリエンスが重要」「デジタルデータでそれらを加速させ、社会と産業を進化させる戦略を考えている」と述べた。
また基本戦略として、以下の3点を挙げた。
① アプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアをそれぞれ分離する「ソフトウェア・デファインド」を変革の軸としながら、既存のバリューチェーンをデジタル化するデジタル・エボリューション
② そこから生まれるデータを生かし、プラットフォームを提供するデジタル・トランスフォーメーション
③ 量子技術を活用し、あらゆるプラットフォームが業界を超えて最適な形でつながるクオンタム(量子)・トランスフォーメーション
東芝が特に強みを持つエネルギー、インフラ、デバイスといった事業領域を中心に、データの力も活用していくとする。
日本の製造業が向かう方向性は妥当なものだ。だが製造業DXをめぐる戦いにあたり、日本企業の武器が従来どおりの「すり合わせ」「現場力」「暗黙知」等では勝ち目がないだろう。
そもそもDXとは、小手先のデジタル化ではなく、事業そのもの、企業そのものを進化させる本質的な革新だ。そこでは、テスラ=イーロン・マスクのような、既存の製造業の常識を疑う、大胆な発想が求められる。アマゾンには顧客中心主義を学びたい。「AWS IoT ツインメーカー」に見るようにアマゾンAWSの強さは、エンタープライズ向けのBtoBでありながらクライアント以上にエンドユーザーの満足にコミットする点にある。
筆者が日本企業に期待するのは、誤解を恐れずにいうならば「BtoB事業者としての誇りを捨てる」ことだ。デジタル化にはあらゆるものを「つなげる」側面があるが、BtoB企業も顧客とスマホなどを介して直接つながり始めた。そして業界の覇権を握るのは、その顧客とのつながりの中で優れたカスタマーエクスペリエンスを提供した企業である。GAFAらメガテック企業の覇権も、彼らがサービス・プロバイダーとして顧客と親密な関係性を築くことで手にしたものにほかならない。ひるがえって日本の製造業はどうだろう。無論、日本の製造業もBtoCに進出してはいる。しかし「連携企業を介して」BtoCサービスを提供することはあっても、消費者と真正面から相対することに及び腰に見えはしないか。テスラの物理学的発想と、アマゾンのカスタマーセントリックは、従来の「日本の製造業」から脱皮できない企業にとって、極めて重要な示唆となるだろう。
執筆者
- 田中 道昭立教大学ビジネススクール教授
Ridgelinez 戦略アドバイザー
※所属・役職は掲載時点のものです